「このままではお店が潰れる…」あなたは今、そうした危機感に苛まれていませんか?
従業員や家族の生活が一変してしまうことは避けなければなりません。
その危機感やプレッシャーは半端なものではありません。
これは経験した人にしかわからないでしょう!でも、この経験があるからこそ、いろいろなことにアンテナを張り試行錯誤することで自分自身だけでなくチームも強くなれると思います。
私は現在、潰れかけの店舗で管理職をしています。先月ついに赤字に転落し、このままでは店舗閉鎖の危機に瀕しています。しかし、「このお店を絶対に守りたい!」という覚悟を胸に、チームを再構築した結果、今月は赤字回避の目途が立ちました。
この記事では、私が赤字店舗の立て直しで実践した、「チームが自ら考え、動き出す」ようになる具体的なステップと、その背後にある「勝利の方程式」をすべて公開します。
もしあなたの職場に同じような課題があるなら、この記事を読み終える頃には、まず「何をすべきか」が明確になっているはずです。
店舗閉鎖の危機!赤字転落した職場の「リアルな課題」
まず、問題の根源を明確にすることが、店舗立て直しの第一歩です。
課題1:なぜ赤字になったのか?管理職が直面した「3つの致命的な現状」
私が管理職として最も危機感を覚えたのは、先月ついに赤字に転落したという結果だけでなく、その赤字が構造的な問題から来ているという事実でした。具体的な分析で浮き彫りになったのは、以下の3つの致命的な現状です。
- データ不在のマネジメント: 売上分析が「昨対比」や「目標との差」といった表面的なもので終わり、時間帯別・商品カテゴリー別の細かな分析がされていませんでした。そのため、「誰に何を指示すれば効率が上がるか」という具体的な施策が立てられず、すべての業務が場当たり的になっていました。
- スキルマップの「曖昧さ」: 従業員一人ひとりの「現在のスキル」と「習得すべきスキル」が完全に属人化しており、誰が何をできるのかが把握されていませんでした。結果、業務の偏りが激しく、人がいない時間帯にはサービスの質が著しく低下するという悪循環に陥っていました。
- 情報共有の「ブラックボックス化」: 本部からの連絡や店舗内の成功事例が、店長や一部のベテランで滞留し、全従業員にオープンに共有される仕組みが欠けていました。これにより、店舗の状況に対する危機意識や、改善施策の目的が末端まで浸透していませんでした。
「このままでは絶対に店舗は守れない」——そう確信した私は、これらの客観的な事実を武器に、次のステップへと動き出すことになります。
課題2:世代によって大きく異なる「危機感の温度差」
従業員の年齢層によって、危機に対する意識はまったく異なっていました。このギャップが、チームを一つにする上での最大の障害でした。
- 60代の従業員: 年金収入もあり、「まぁ何とかなるだろう」と、危機感は薄い。
- 30代の従業員: 転職を視野に入れており、「他人事」のような反応が目立つ。
- 40〜50代の従業員: 長年勤めており、「お店を守りたい」という気持ちが強く、最も危機感を持っている。
この「お店を守りたい」という熱意を持った40〜50代を、チームの再構築における中核層として特定することが、私の最初の戦略となりました。
赤字回避を実現した「チーム再構築」の3つのステップ

危機感を共有した後は、具体的な行動でチームのエンジンをかけ直しました。
ステップ1:管理職の「覚悟」を伝え、中核層(40代・50代)を巻き込む
私は「絶対に店舗を潰さない」という覚悟を繰り返し伝え、特に熱意のある40〜50代を中心に「今、何ができるか?」「何をすべきか?」を一緒に考える場を設けました。
【結果】
- 建設的な意見が40〜50代から多く出るようになり議論が加速。
- その前向きな変化に感化され、30代の従業員も徐々に協力的になりました。
ステップ2:個々の「スキル」を可視化し、成長を“見える化”する
次に、全従業員の「稼ぐ力」を高めるため、個々のスキルを明確にしました。
- スキル一覧の作成: 現在のスキルと、今後習得してほしいスキルを一覧表にまとめました。
- 目標の明確化: 個人の目標と、それが店舗の立て直しにどう繋がるかを明確にしました。
- 成長の見える化: スキルアップの進捗を共有し、個人の成長がチーム全体のスピード加速に貢献していることを実感させました。
ステップ3:年配層(60代)には「後継育成」という役割を与える
危機感の薄かった年配層には、無理な改革を求めず、「経験を若手に伝える」という新しい役割(後継育成)を与えました。これにより、世代間の協力関係が生まれ、チームの一員としての貢献意欲を引き出すことに成功しました。
【勝因の分析】チームの成長力を「無限」にする勝利の方程式

一連の取り組みを通じて、私はどんな職場でも通用する「勝利の方程式」を発見しました。
作業効率の向上×コミュニケーションを高める=無限の成長力
この方程式は、ただ効率化するだけ、ただ仲良くするだけでは成り立ちません。両方の要素が掛け合わされることで、チームは爆発的な成長力を発揮します。
法則1:作業効率を高めるための「共通言語」と「PDCAの高速化」
「作業効率を高める」とは、単にムダを省くだけでなく、チーム全体で「正しく働くための共通認識」を持つことを意味します。私たちが実践したのは、以下の2点です。
1. スキル・目標の「共通言語化」による無駄の排除
前の章で述べた「スキルの可視化」は、誰がどの業務を担うべきか、どの業務にリソースが不足しているかを一目でわかるようにしました。これにより、特定のベテランへの業務集中が解消され、全体の業務負荷が分散しました。また、目標が明確になったことで、従業員は「何をすれば店に貢献できるか」を自分で判断できるようになりました。
2. 成長を「見える化」したことによるPDCAの高速化
個人のスキルアップの進捗を共有した結果、従業員は自分の成長を実感できるようになりました。この「成長が見える」状態が、モチベーションを向上させ、「試行 → 改善」のサイクル(PDCA)を加速させました。誰かが改善した小さなノウハウが、すぐにチーム全体に共有・実践される環境が整ったことで、チームの作業効率は飛躍的に向上しました。
法則2:自律的なチームを育む「安心」と「信頼」の土台
部下が自ら動くようになるには、まず「安心」と「信頼」の土台が不可欠です。
「コミュニケーションを高める」とは、雑談を増やすことではありません。部下が「自ら動く」ための土壌づくりです。私たちが重視したのは、管理職としての以下の役割です。
1. 「安心」の土台:感情の理解と心理的安全性
部下が新しい挑戦や改善提案を躊躇するのは、「失敗を恐れる」からです。私は面談や日々の会話で、目標の共有だけでなく、従業員の「感情の理解」に努めました。「あなたの努力は認めている」「失敗しても挑戦を評価する」というメッセージを伝え続けたことで、「安心」して意見が言える心理的安全性の高い環境が構築されました。
2. 「信頼」の土台:管理職の「透明性」と「共創」
管理職が「覚悟」を伝えるだけでなく、「今、店が抱える課題」を正直に、透明性高く共有することが、従業員との間に「信頼」を築きました。特に中核層(40代・50代)と一緒に「どうすればお店を守れるか」を「一緒に考える場」を設けたことで、「上から指示された」のではなく「自分たちが決めた」という当事者意識(オーナーシップ)が芽生えました。
まとめ:店舗を立て直す管理職に求められる「最初の一歩」
私の行動は、「絶対に店舗を潰さない」という管理職としての揺るぎない覚悟から始まりました。
その強い想いが、時間をかけて、一人ひとりの従業員に伝わり、チームを動かす原動力となりました。赤字店舗を立て直し、チームを活性化させるために、特別なスキルは必要ありません。
もしあなたの職場にも同じような課題があるなら、まずは“チームの声を聞く”ことから始めてみてください。
覚悟を持ち、彼らの声に耳を傾ける。そこから、あなたの職場の変化の兆しが、きっと見えてくるはずです。
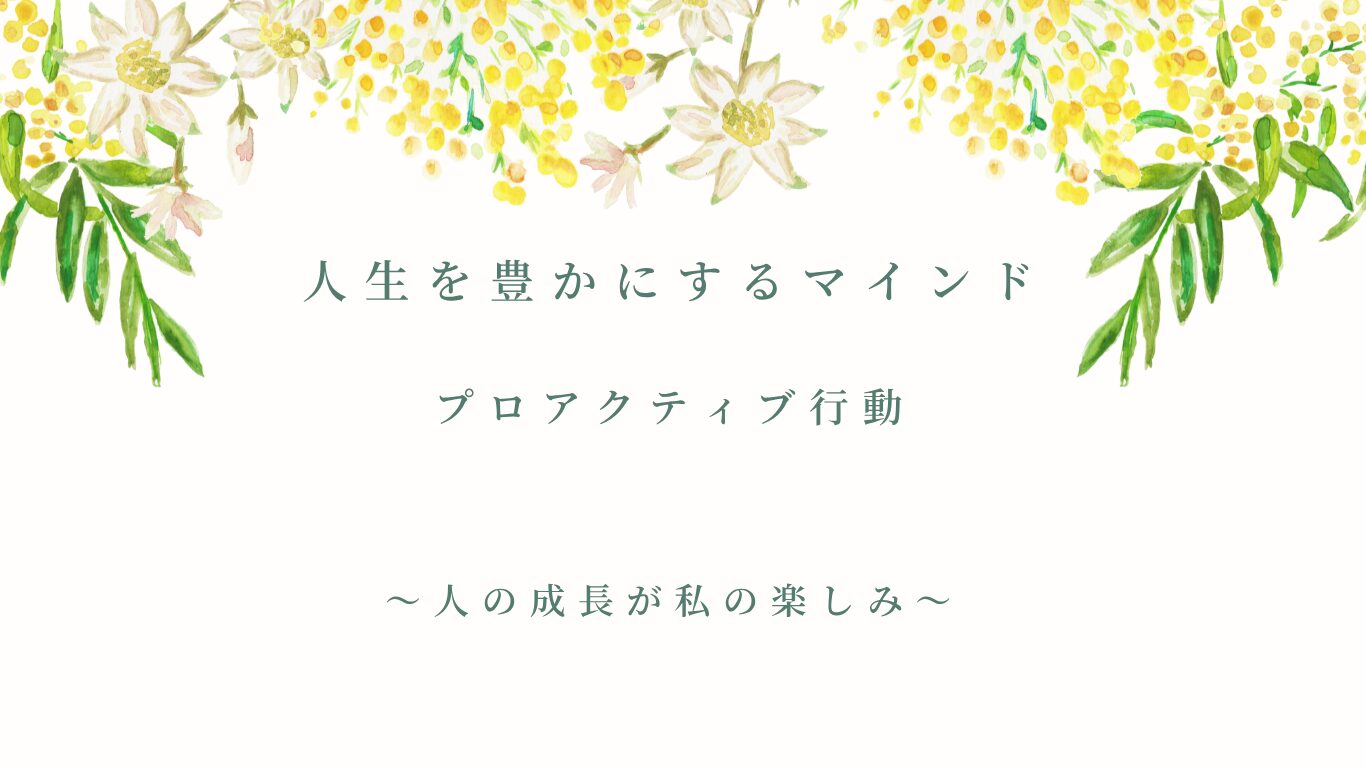
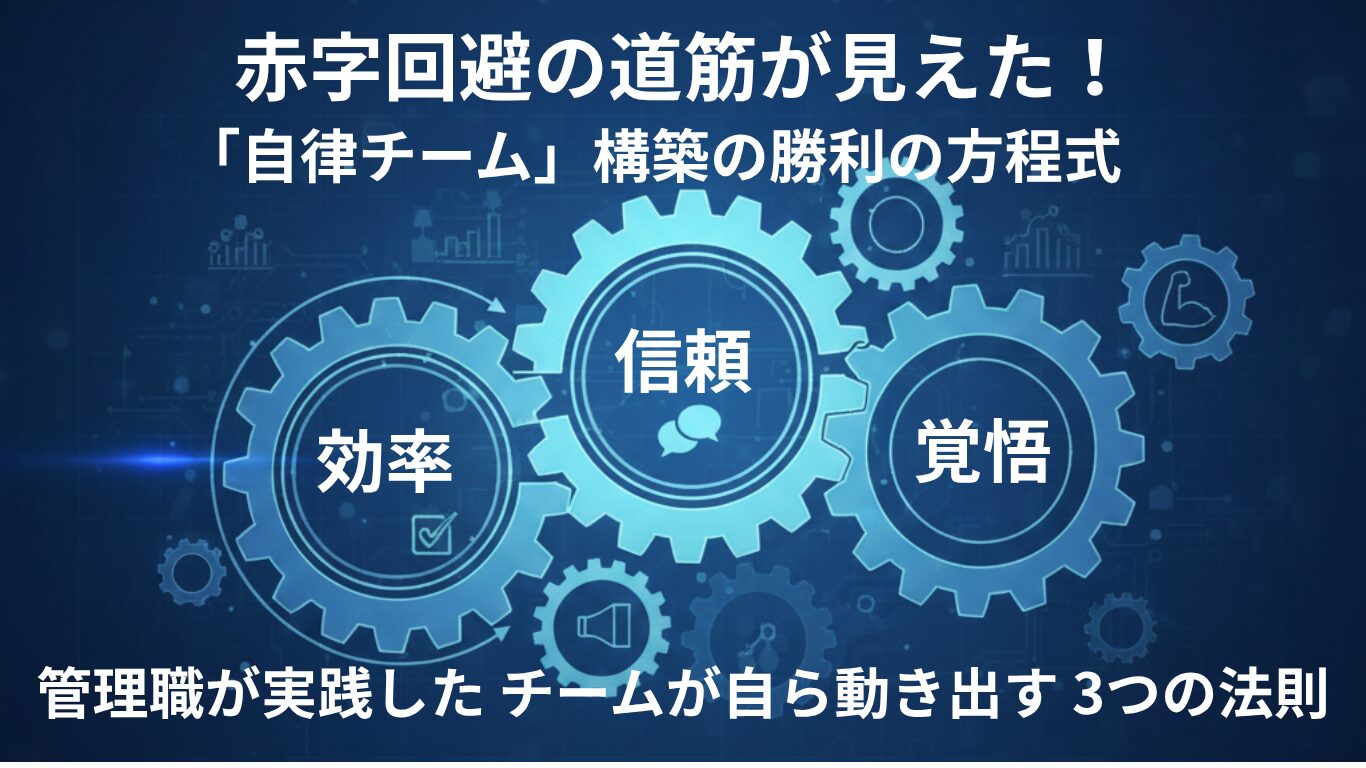


コメント