「人と話すのが苦手」「会話が続かない」「緊張して何も言えない」
そんな自分がイヤでイヤで仕方がない。
「もっと人と話せるようになりたい!」「私の思いや考えを上手に話せるようになり会話を楽しみたい!」「人前でも緊張せず自分を出したい!」
そんな自分になりたいという希望はありませんか!?
そう願いながらも、「でも自分には無理かも…」と諦めていませんか?
安心してください!人は何歳からでも変わることができます。
実際、心理学の研究でも「コミュニケーション能力は生まれつきではなく、後天的に伸ばせるスキル」と明らかになっています(日本労働政策研究・研修機構, 2006)。
強く「自分を変えたい!」と思い、行動に移すほど何歳でも人は変えることができます。
私も以前は会議で指名されても発言できずに落ち込む日々を過ごしていました。
しかし心理学的なアプローチを学び、少しずつ行動を変えることで今では人との会話を楽しめるようになりました。
この記事では“コミュ障克服の3ステップ”を紹介します。

🪞ステップ① 自分の「コミュニケーション傾向」を理解する
まず大切なのは、「自分は何が苦手なのか」を客観的に知ることです。
話すのが苦手なのか、相手の反応が怖いのか、沈黙が苦手なのか——原因は人それぞれです。
🔍 心理学的な根拠 〜自分に気付き自分を知る〜
群馬大学の研究(荒川, 2017)では、大学生を対象に「コミュニケーション・スキル尺度(ENDCOREs)」を使って自己理解を促すと、対人不安の軽減につながることが報告されています。
つまり、「自分はどういう傾向があるのか?」を把握すること自体が克服の第一歩です。
💡実践ポイント
- 苦手な場面を想像しノートに書き出してみる
- 「緊張する瞬間」を具体的に思い出してみる
- 自分の強み(聞き上手・気配りなど)も一緒に整理する
🗣 ステップ② 「話す」よりも「聴く」から始める
人との会話は、話す力よりも「聴く力(傾聴)」のほうが重要です。
実は、相手に「この人、話しやすい」と思ってもらうだけで、会話のハードルはぐっと下がります。
🔍 「聞くチカラ」が上がればコミュニケーション力も上がる
神奈川県教育研究所(2014)の調査では、相づち・共感・うなずきなどの聴き方の工夫が会話の円滑さを高めることが示されています。
また、アメリカ心理学会(APA)の報告によると、「傾聴を重視したコミュニケーション訓練(Active Listening Training)」は、対人関係満足度を有意に向上させる効果があります。
💡実践ポイント
- 「それ、わかる」「なるほど」と共感の相づちを使う
- 相手の話の“感情”を繰り返す(例:「緊張したんですね」)
- 無理に話題を増やさず、相手のペースに合わせる
「聞くチカラ」と合わせて「話すチカラ」も身につけると更にコミュニケーション力が上がります。
🎙 『話すチカラ』齋藤孝 × 安住紳一郎
TBSアナウンサー・安住紳一郎さんと教育学者・齋藤孝先生が語る、“人に伝わる話し方”の極意。
会話やスピーチが苦手な人でも、「どう話せば相手の心に届くのか」がわかりやすく学べます。
言葉の選び方・声の出し方・表情まで、すぐ実践できる内容ばかり。
まるで安住さんのラジオを聴いているように楽しく読めて「話すって楽しい」と思える一冊です。

💬 ステップ③ 少しずつ「行動」で慣らす
コミュニケーション能力は「性格」ではなく「スキル」として鍛えられることが分かっています。
実際、社会的スキル訓練(Social Skills Training:SST)は、世界中で効果が実証されています。
🔍 訓練をすれば改善効果あり!
2021年のメタ分析(Gates et al., Journal of Autism and Developmental Disorders)によると、成人を対象とした社会的スキル訓練には中程度の改善効果(効果量 d ≈ 0.5)が認められています。
また、日本労働政策研究・研修機構(JIL, 2006)も、「社会的スキル訓練は職場での人間関係改善に有効」と報告しています。
💡実践ポイント
- まずは「1日1回あいさつ」など小さな行動を決める
- 話す相手を限定(職場の1人、店員さんなど)
- できたら自分を褒める(成功体験を積むことが最重要)
🌱 まとめ:練習で克服できる!

「コミュ障を克服する」と考えるよりも“コ
ミュニケーション筋”を鍛えるというイメージが近いかもしれません。
心理学研究の多くは、「人との関わり方はトレーニングで変わる」と結論づけています。
疲れた時は一人になって休憩しても構いません。
焦らず、自分のペースで“話す・聴く・慣れる”を繰り返していきましょう。
一歩踏み出すだけで、世界は少しずつ変わり始めます。
📚 参考文献
- 荒川美香(2017)『大学生のコミュニケーション・スキルの特徴に関する研究』群馬大学教育学部紀要
- 神奈川県教育センター(2014)『コミュニケーションを促す“聴き方”に関する研究』
- Gates et al. (2021). A Systematic Review and Meta-analysis of Social Skills Training for Adults with ASD, JADD
- 日本労働政策研究・研修機構(2006)『コミュニケーション・スキルの重要性』JIL報告
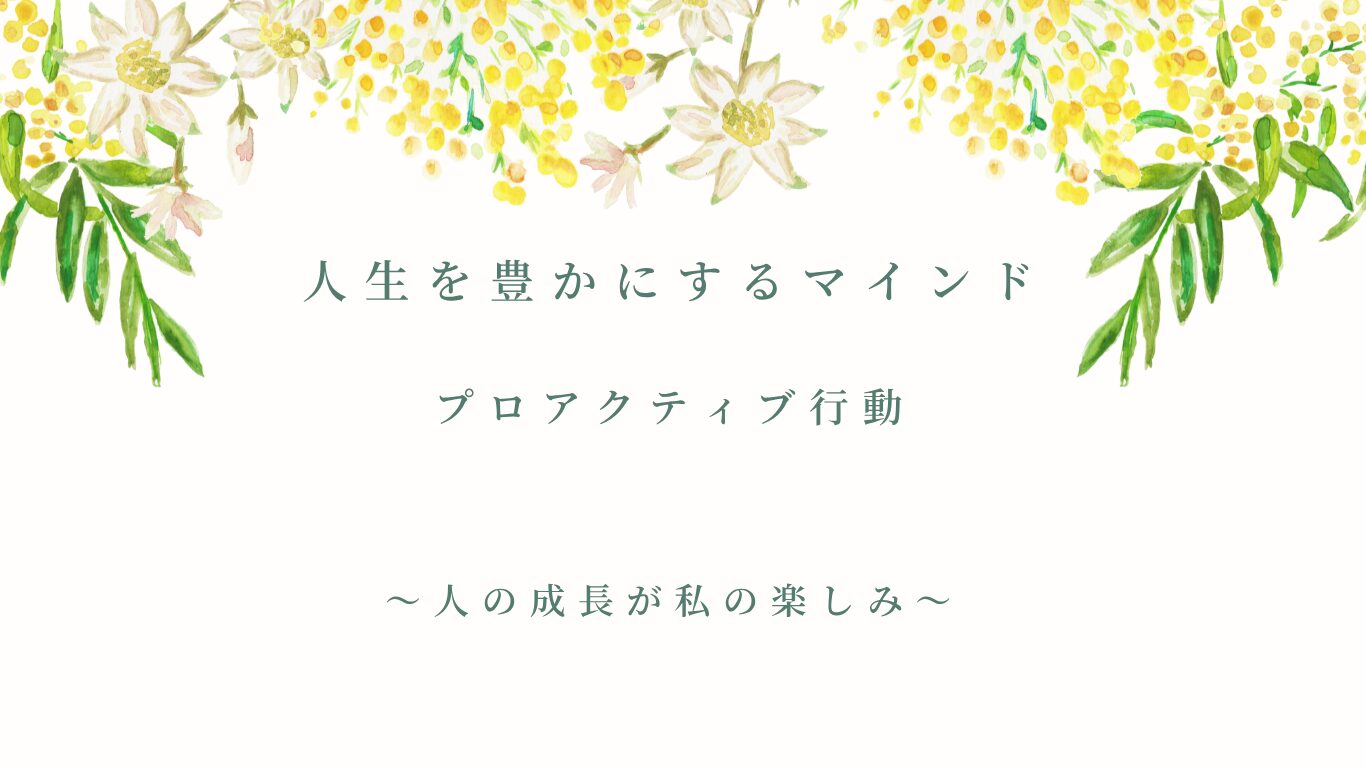
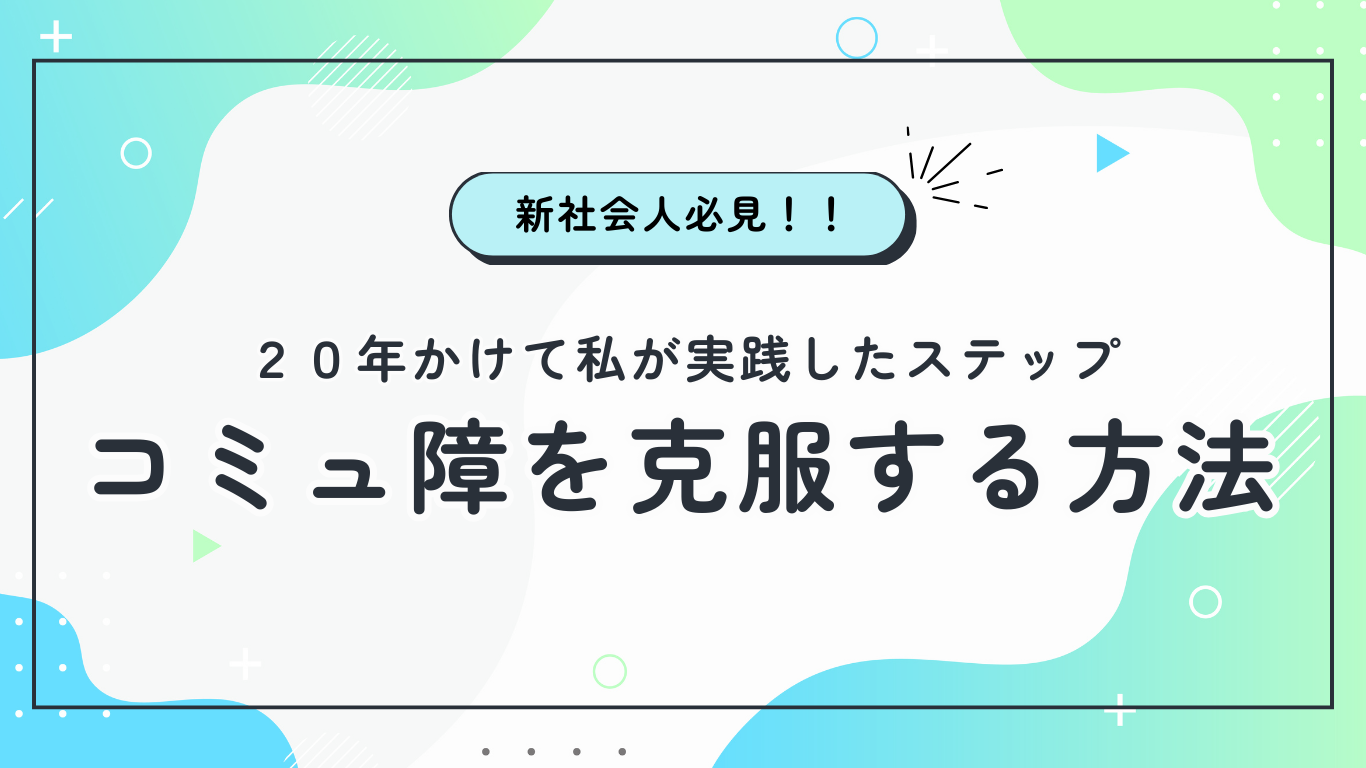


コメント